【 介護保険 】制度は、高齢者の自立支援を目的とした日本の社会保障制度の柱のひとつです。そして、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といったリハビリ専門職がこの制度の中で果たす役割は年々大きくなっています。
しかし、医療現場とは異なる介護分野のルールや仕組みに戸惑う若手コメディカルも少なくありません。
この記事では、介護保険制度の基本的な構造から、訪問・通所リハビリでの実務的な活用ポイントまで、エビデンスをもとに丁寧に解説します。現場で即活かせる知識を整理し、制度に強いリハビリ職を目指しましょう。
📊 統計データ
厚生労働省「令和4年度 介護保険事業状況報告(年報)」によると、
- 介護サービス利用者数は約626万人(要介護・要支援含む)
- このうち訪問リハビリテーション利用者数は約15.6万人、
- 通所リハビリ利用者数は約52.5万人であり、全体の約1割を占めます。
このようにリハビリ職が介護保険制度の中で関わる機会は広がり続けています。
介護保険制度とは?
日本の高齢化率は2024年現在、29.1%を超え、世界でも最も高齢化が進む国のひとつです。これに伴い、加齢に伴う介護ニーズへの対応が社会的課題となり、2000年に創設されたのが介護保険制度です。
介護保険制度は、「高齢者の尊厳の保持と自立支援」を基本理念とし、40歳以上のすべての国民が保険料を負担し、介護が必要になった際に給付を受けられる社会保険方式の制度です。市区町村が保険者(運営主体)となり、要介護・要支援認定を受けた人に対して、必要な介護サービスが提供されます。
制度の目的は単なる「介護」ではなく、「できる限り在宅で生活を継続し、自分らしく暮らし続ける」ことの支援です。そのため、訪問系や通所系、施設系サービスのほか、リハビリテーションや福祉用具貸与、住宅改修といった自立支援的なアプローチも広く含まれています。
✅ 医療保険との違い
医療保険と介護保険の違いとして最も重要なのは、「目的」と「主たる支援対象」です。医療保険は治療・回復を目的とした制度であり、診断や治療行為が中心となります。一方、介護保険は生活支援と機能維持・改善を目的としており、利用者の生活状況や環境、家族背景をふまえた長期的支援が前提となります。
特にリハビリ職にとっては、医療保険で行う急性期や回復期のリハビリと、介護保険での生活期リハビリの目標や関わり方の違いを理解することが重要です。
✅ 要介護認定の流れ
介護保険サービスを利用するためには、まず市区町村に申請し、要介護認定を受ける必要があります。以下がその流れです。
- 申請(本人・家族・ケアマネジャーが行う)
- 認定調査(訪問による聞き取り調査)
- 主治医意見書の提出(医学的観点からの評価)
- 介護認定審査会での判定
- 要介護・要支援度の決定(非該当含む)
このように、医学的要素と生活機能評価の両面から判定されるのが特徴です。
✅ 自立支援を軸とした介護
介護保険制度では、支援が必要な状態を前提にしつつも、「残存能力の活用」「活動性の向上」を重要視しています。特に、リハビリテーションの視点は制度創設当初から明記されており、介護予防やリハビリ職の参画は制度上の核のひとつとされています。
また、近年は「科学的介護」が注目され、LIFE(科学的介護情報システム)に基づくPDCAサイクルの導入や、リハビリテーション専門職によるエビデンスベースの支援が重視されつつあります。
厚生労働省「介護保険制度の概要」🫱参考
「福祉・介護地域包括ケアシステム」🫱参考
介護保険について分かりやすく学びたい方におすすめ(イラストが多め)📚
『最新 図解 介護保険のしくみと使い方がわかる本 』(牛越博文、講談社)
🚗 リハビリ職が関わる介護保険サービス
介護保険制度の中で、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)といったリハビリ専門職は、多岐にわたる役割を担っています。特に、生活期における身体機能・活動・参加の支援を通して、自立支援・重度化防止を実現するための中核的な存在です。
ここでは、リハビリ職が関わる主なサービスとその特徴について解説します。
✅ 訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションは、利用者の自宅を訪問して行うリハビリサービスです。主治医の指示のもと、リハ職が定期的に訪問し、生活環境に即した訓練を提供します。
主な内容には、関節可動域訓練、筋力訓練、バランストレーニング、移動動作の練習、家事動作訓練などが含まれます。また、家屋内での移動手段の確保や福祉用具の選定、介護者への指導なども重要な業務です。
訪問リハの強みは、「実際の生活場面で直接訓練できる」点にあり、施設内訓練では得られにくい現実的な機能改善や介護負担軽減が可能です。

『在宅認知症高齢者を対象とした訪問リハビリテーションの有効性』🫱参考
✅ 通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーションは、医療機関や介護老人保健施設などに設置されたリハビリ専用スペースに通い、日中に機能訓練を受けるサービスです。対象は、比較的移動能力が保たれている要支援・要介護高齢者です。
内容には、個別訓練、集団体操、食事・入浴の介助、栄養指導、口腔ケアなどが組み合わされることが多く、単なる「運動の場」ではなく生活機能全体の向上を目指す包括的な支援が行われます。
また、多職種(看護師、介護職、管理栄養士、ケアマネジャーなど)と連携しながら、医学的な知見と生活支援を結びつける拠点的役割を果たします。
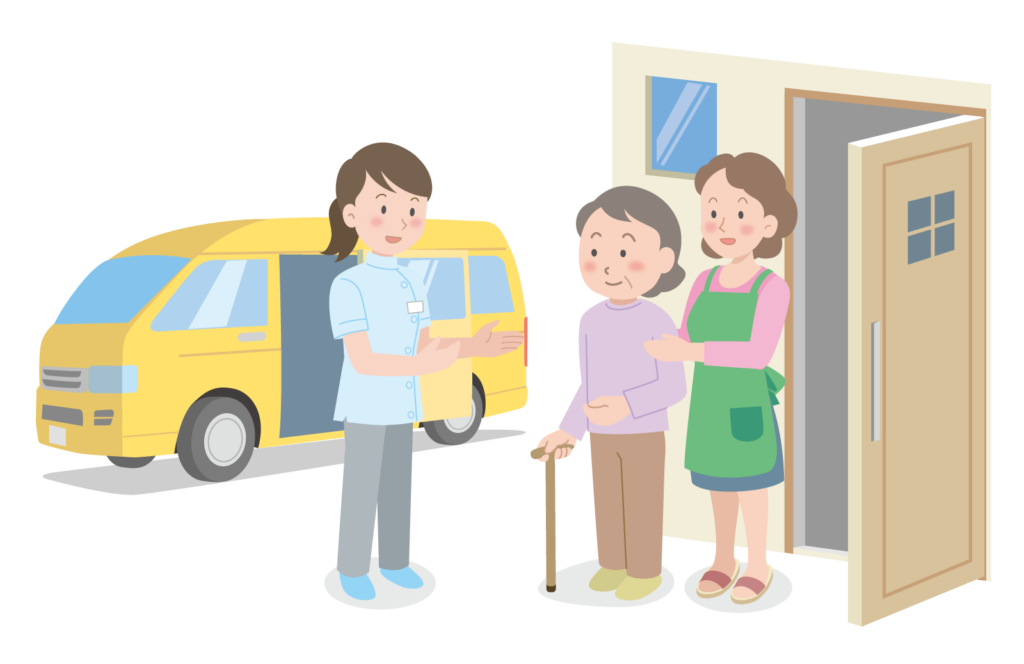
✅ 介護予防リハビリ(要支援対象)
要支援1・2の認定を受けた方に対しては、「介護予防」を目的としたリハビリサービスが提供されます。これは、介護度の進行を防ぎ、地域で自立した生活を維持することを目的としています。
たとえば、体力低下・フレイル・ロコモティブシンドロームに対する個別対応や、認知機能低下への生活支援的アプローチなどが含まれます。また、保健師や地域包括支援センターとの協働も重要になります。
✅ 福祉用具の選定と助言
介護保険には、福祉用具貸与・購入の制度があり、以下のような用具が対象です。
- 車椅子・歩行器
- 特殊寝台(電動ベッド)
- ポータブルトイレ
- 入浴用いす・スロープ・手すり 等
リハ職は、これらの用具が利用者のADL(日常生活動作)向上に資するかどうかを評価・選定する立場にあります。たとえば、屋内の移動困難に対しては滑りにくい歩行器や車椅子、夜間のトイレ動作に対してはポータブルトイレの導入など、具体的な生活課題に即した用具選定が求められます。
『高齢者の移動を支援する用具について』🫱参考
介護保険でレンタル・購入できる福祉用具について知りたい🔎
✅ 住宅改修への関与
介護保険では、要支援・要介護者の住宅改修に対して最大20万円(1割〜3割負担)の補助があります。対象工事には以下のようなものが含まれます。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消(スロープや簡易リフトの導入など)
- 滑りにくい床材への変更
- 引き戸への変更

リハ職は、改修前に身体機能評価・住環境評価を行い、「どの場所にどの手すりが必要か」「転倒リスクはどこにあるか」といった生活機能視点からの助言を行うことが求められます。住宅改修業者や福祉住環境コーディネーターとの連携も重要です。
『在宅高齢障害者の住宅改修計画立案に関連する要因』🫱参考
✅ 実務の中でのまとめ
リハビリ専門職にとって、介護保険制度内での役割は単なる訓練提供ではありません。生活課題を捉え、機能的・環境的な改善策を総合的に提案・実施することが求められます。そのためには、制度の理解、他職種との連携、利用者本位の視点が欠かせません。
リハビリ視点からの介護保険について学べる一冊📚
『介護保険とリハビリテーション』(千野直一 、安藤徳彦、金原出版株式会社)
☎️ ケアマネジャーとの連携とリハビリ計画書
介護保険制度の中でリハビリ専門職がサービスを提供する際、必ず関わるのがケアマネジャー(介護支援専門員)の存在です。リハビリ職は、ケアマネとの情報共有・連携を通じて、利用者にとって実効性のある支援計画を形成していくことが求められます。
✅ ケアプランとの関係
介護保険サービスはすべて、「ケアプラン(居宅サービス計画)」に基づいて提供されます。このケアプランはケアマネジャーが中心となって作成し、利用者の心身状況、家族の希望、生活環境、医師の意見を反映させながら、適切なサービス種別・頻度・内容を定めます。
リハビリ職が訪問リハや通所リハを提供する際には、ケアプランとの整合性をもった個別のリハビリ計画を作成しなければなりません。この計画は、単なる訓練メニューではなく、「どのような日常生活課題を改善するか」「生活のどの場面に着目するか」といった、生活支援型のゴール設定が重要です。
✅ リハビリ専門職が作成する計画書とは?
訪問リハビリや通所リハでは、リハ職が下記のような計画書を作成します:
- リハビリテーション実施計画書(個別機能訓練計画書)
- 目標設定と評価(ADL・IADL・参加・QOL)
- 提供頻度、内容、方法、使用機器の記載
- モニタリング・再評価の予定
この計画書は、ケアマネに提出され、ケアプラン全体との整合性が確認される必要があります。したがって、ケアマネが理解しやすく、生活場面とのつながりが明確な内容であることが大切です。
✅ サービス担当者会議での役割
サービス開始時や大きな変更時には、「サービス担当者会議」が開かれます。ここでは、ケアマネ、医師、看護師、リハ職、介護職、家族などが一堂に会し、利用者の現状と課題、目標を共有します。
この場で、リハビリ職には以下のような役割があります
- 利用者の身体機能評価と生活機能評価の説明
- 「歩行能力はあるが、浴室での転倒リスクが高い」など、具体的な場面への言及
- 短期・中期の目標提案(例:「屋外歩行距離を増やす」「調理動作を一部再開」)
- 福祉用具や住宅改修の提案と根拠提示
発言内容は記録に残るため、専門的な視点と、家族や他職種にもわかりやすい言葉の両立が求められます。
✅ 情報提供書・フィードバックの重要性
定期的にリハビリ内容や経過を文書で報告する「情報提供書」も、ケアマネとの信頼関係構築において重要です。ケアマネは医療職ではないため、難解な専門用語よりも、「できることが増えた」「介助量が減った」といった生活レベルでの変化が重視されます。
また、以下のような報告スタイルが推奨されます
- 「●月時点では自立不可だったが、現在は屋内歩行は可能に」
- 「下肢筋力改善によりトイレ動作にかかる時間が半減」
- 「調理中の立位保持が困難になってきたため、今後の介護量増加が予測される」
これにより、ケアプランの再構築や他サービスとの連携判断がしやすくなります。
厚生労働省『介護サービス計画(ケアプラン)について』
このように、ケアマネとの情報共有と生活視点での連携は、介護保険下でのリハビリの質を左右します。
専門性を保ちつつ、「暮らしに根ざした支援」としてケアに関わることが、リハ職に求められています。
📙 リハビリ職が知っておくべき注意点と法制度
介護保険制度の中でリハビリを提供する際には、医療保険と介護保険の違いだけでなく、法的な制限や実務上の注意点を把握しておくことが重要です。特に、制度の「隙間」によってトラブルや請求漏れが起きることもあるため、現場で役立つ観点から解説します。
✅ 医療保険との同日併算制限
リハビリ職が最も注意すべき制度上の制限のひとつが、「医療保険と介護保険の同一サービスの同日併算は不可」という原則です。たとえば以下のようなケースが対象になります。
✕ 例:
- 午前中に病院で外来リハビリ(医療保険)
- 午後に自宅で訪問リハビリ(介護保険)を受ける
この場合、原則として片方しか請求できないため、事前にサービス提供者間での調整が必要です。
現場では、医療機関側が医療保険の外来リハを提供し続ける一方、訪問リハ事業所が併算不可を知らずに提供・記録し、後から減算・返戻となる事例もあります。
引用:厚生労働省「介護給付費実態調査」
✅ 医療保険から介護保険への切替タイミング
急性期・回復期病院でのリハビリ(医療保険)が終了した後、自宅や施設へ戻る際に、介護保険へのリハビリ切替が必要となる場合があります。
しかしこのとき、「退院後に訪問リハや通所リハをすぐに導入できるか?」という問題が発生します。要介護認定をすでに受けていればスムーズに移行できますが、認定が未取得の場合は、要介護認定申請→審査→認定決定(最短でも1〜2週間)というタイムラグが生じるため、空白期間ができる可能性があります。
対応のポイント:
- 入院中にケアマネや地域包括と連携し、退院前に要介護認定を申請しておく
- 医療保険での訪問リハ(退院直後)と、介護保険サービスへのスムーズなバトンタッチを計画
- 「退院・退所加算」などの制度を活用し、地域包括ケアシステムの連携を生かす
✅ 自費リハビリとの違いと注意点
近年、介護保険制度外で提供される「自費リハビリサービス」も注目されています。しかし、介護保険制度下で支給限度額を超えた利用者に対して、安易に自費リハを勧めるのは注意が必要です。
介護保険と並行して提供する場合には、以下の点を明確にしなければなりません。
- 保険内サービスとの内容・目的の違い(同一内容の繰り返しは不可)
- 契約・料金体系の明示(十分なインフォームドコンセントが必要)
- 利用者や家族への誤解・不安が生じない配慮
厚労省の通知でも、「介護保険外サービスを併用する際は、保険との区別を明確にすること」とされており、制度の趣旨を外れた提供は適切でないと明記されています。
✅ 科学的介護・LIFEへの対応
2021年度から本格導入された「科学的介護(LIFE:Long-term care Information system For Evidence)」では、リハビリ職にもデータ提出が求められるケースがあります。
具体的には、ADL維持等加算やリハビリテーションマネジメント加算に関連し、FIMやバーセルインデックスなどの機能データを定期的に提出・分析・改善することが求められています。
このLIFE対応を通じて、リハビリ職もエビデンスに基づく介護サービス提供者として制度に深く関与していくことが求められています。
厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)について」
✅ 制度を知ることは実践の武器になる
リハビリ職が介護保険制度を理解することは、単なる「知識」ではなく、現場の支援力を高める実践力そのものです。制度を誤解したまま介入すれば、利用者の利益を損なうだけでなく、事業所にとってもリスクとなります。
制度の正しい理解と、現場での応用力を養うことで、本当に必要とされる支援者として活躍することができるのです。
💡 まとめ|制度を理解して現場のリハビリを強化しよう
介護保険制度は、単なる「介護を受けるための仕組み」ではなく、高齢者が自立した生活を続けるための支援基盤です。そしてその中で、リハビリ専門職が果たす役割は、年々大きく、そして複雑になっています。
医療保険との違い、要介護認定、訪問・通所リハビリ、福祉用具の選定、住宅改修、ケアマネとの連携、科学的介護(LIFE)対応まで――。こうした要素を体系的に理解し、制度の中でリハビリの専門性をどう活かすかを常に意識することが重要です。
特に現場では、「制度がこうだからできない」と制限を感じる場面も少なくありません。しかし、制度の本質や運用の工夫を知ることで、「できることが増える」「関係職種との協力がスムーズになる」「利用者の生活が改善する」といった、よりよい支援につなげることができます。
また、制度は改正が続くため、最新情報を常にキャッチアップする姿勢も求められます。制度を理解し、使いこなせるリハビリ職は、現場でも信頼され、チーム全体の質の向上に貢献する存在となるでしょう。
今後、地域包括ケアや在宅医療の推進がますます進む中で、リハビリ職は「制度に強い専門職」であることが求められています。制度を知り、制度を活かし、制度の枠を超えて支援する力を、日々の実践の中で磨いていきましょう。



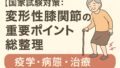
コメント