国家試験では、【 変形性膝関節症 (knee osteoarthritis, 膝OA)】が定期的に出題されており、整形外科領域の必須項目です。単なる解剖や診断知識だけでなく、疫学的知見や運動療法の有効性、生体力学的な理解も求められるため、出題ポイントの整理が得点に直結します。
本記事では、変形性膝関節症の出題傾向を分析し、国家試験で問われやすいポイントとその背景、練習問題と解説を交えて学んでいきます。
📊 統計
変形性膝関節症は日本において極めて頻度の高い運動器疾患であり、厚生労働省や整形外科学会のデータによると、症状を有する患者は約800万人、潜在的な患者を含めると約3000万人にのぼります。🫱参考1/参考2/参考3
また、代表的な地域疫学研究「ROAD study」によると、60歳以上の女性の有病率は50%を超え、男性の約4倍と報告されています。膝OAの発症には加齢・性別(女性)・肥満・遺伝・膝外傷歴などが関与し、整形外科疾患のなかでも生活の質(QOL)に大きな影響を及ぼす点が国家試験でも強調されています。🫱参考4/参考5/参考6
変形性膝関節症について詳しく知りたい💡別記事🫱『変形性膝関節症|若手医療従事者のための完全ガイド【手術・リハ・国家試験対策も】』でも詳しく解説しています🚶
🎓 国家試験での出題傾向
変形性膝関節症(以下、膝OA)は、理学療法士・作業療法士国家試験をはじめ、柔道整復師、看護師、医師国家試験でも頻出の整形外科疾患です。とくに理学療法士・作業療法士国家試験では、膝関節の疾患として最も出題頻度が高い部類にあり、毎年のように出題されています。
国家試験での出題は、おおむね以下の3パターンに分類されます。
① 疫学・発症リスクに関する問題
たとえば以下のような出題です。
「変形性膝関節症の発症リスクとして適切でないのはどれか」
「有病率が高い年齢層や性別について正しいものはどれか」
この領域では、女性・高齢・肥満・遺伝的素因・膝外傷歴などがポイントです。J-STAGEに掲載された松代町でのコホート研究や、全国疫学調査(ROAD study)によって裏付けられた疫学データが理解のカギとなります。
実際に、2022年の理学療法士国家試験では「危険因子」についての出題があり、基本的な疫学知識が問われました。
② 画像診断や病態に関する問題
変形性膝関節症は画像診断と病態生理が密接に関連しており、国家試験では以下のような出題がみられます。
「変形性膝関節症の初期X線所見として最も適切なものはどれか」
「Kellgren-Lawrence分類について正しい組み合わせを選べ」
国家試験では、X線画像での骨棘形成、関節裂隙狭小化、骨硬化、骨嚢胞といった特徴的所見の順序を正確に理解しているかが問われます。また、K-L分類のグレード判断は、臨床だけでなく試験でも定番の知識です。
③ 保存療法・手術適応・歩行分析に関する問題
リハビリ職種の国家試験では、治療方法や歩行分析との関連も問われます。
「保存療法として最も適切なのはどれか」
「歩行中に膝内反モーメント(KAM)が増大する因子として正しいのはどれか」
「手術療法の適応として適切なものを選べ」
ここでは、大腿四頭筋トレーニング・体重管理・ヒアルロン酸注射・人工関節置換術(TKA)の適応や有効性を把握しているかが重要になります。さらに近年は、生体力学(KAM、スラスト)と病態の進行の関係も問われるようになってきており、「力学的な観点からの理解」も得点差を生むポイントです。
✅ 出題傾向のまとめと対策のコツ
| 項目 | 出題頻度 | 備考・対策ポイント |
|---|---|---|
| 疫学・リスク因子 | 高 | 高齢女性、肥満、運動不足など。確実に押さえる |
| 病態・画像診断 | 高 | K-L分類、X線所見の順序などに注意 |
| 保存療法・手術 | 中〜高 | NSAIDs外用・運動療法・TKAの適応を理解 |
| 生体力学(歩行分析) | 中 | KAMや歩行時の負荷と進行の関係を把握 |
| 鑑別・併存疾患 | 中 | 半月板損傷、骨壊死、関節リウマチとの違い |
特に、選択肢の中から正しいものを選ぶタイプの問題が多く、一部の知識ではなく「全体像の理解」が重要となります。また、過去問に出た知識が数年おきに繰り返し出題される傾向があり、基本的な知識を確実に習得することが得点への最短ルートです。
疾患の理解には分かりやすいこの一冊📚
『病気がみえる vol.11 運動器・整形外科 第2版』(医療情報科学研究所、MEDIC MEDIA)
🔎 出題ポイント解説:重要5テーマ
国家試験では、変形性膝関節症に関する問題が多岐にわたって出題されますが、特に問われやすい重要テーマを5つに絞って解説します。各項目には実際に出題されやすい例を含め、理解と記憶に残りやすい構成としています。
(1)疫学と危険因子
📝出題例
「変形性膝関節症の危険因子として最も関連性が高いのはどれか。」
✅解説
変形性膝関節症の発症・進行に関与する代表的な危険因子は以下のとおりです。
- 加齢:60歳以上から有病率が急増。特に女性に多い。
- 性別:男性1に対して女性4の割合で多く、エストロゲン減少との関連も指摘されている。
- 肥満:BMI25以上でリスクが有意に上昇。メカニカルストレスおよび炎症性サイトカインの影響。
- 遺伝的素因:特に女性における家族歴が有病率と相関。
- 既往歴:膝靭帯損傷や半月板損傷の既往は発症リスクを高める。
参考🫱膝関節疾患—内側型変形性膝関節症における危険因子について—松代膝検診の結果から
(2)病態と画像診断
📝出題例
「変形性膝関節症の初期X線所見として正しいのはどれか。」
✅解説
膝OAの画像所見は病期によって特徴的であり、順序を押さえることが重要です。
- 初期:骨棘形成(osteophyte)が最も早期に出現。
- 中期:関節裂隙狭小化(内側に多い)。
- 進行期:軟骨下骨硬化、骨嚢胞形成。
また、Kellgren-Lawrence分類(K-L分類)は、Grade 0~4の5段階評価で、Grade2以上が「OAあり」と診断されます。
国家試験ではこの分類の知識が問われるだけでなく、X線所見と照らし合わせる応用問題も出題されます。
参考🫱日本整形外科学会. 変形性膝関節症診療ガイドライン 第3版. 2023年.
(3)保存療法と手術療法
📝出題例
「保存療法が無効な場合の治療として適切なのはどれか。」
✅解説
変形性膝関節症の治療は段階的に進めるのが原則です。
- 保存療法:
- 運動療法(大腿四頭筋の筋力強化)が第一選択。
- NSAIDs外用薬は高齢者にも安全性が高い。
- 関節内ヒアルロン酸注射は炎症抑制や滑液改善に有効。
- 手術療法:
- 保存療法で改善しない進行例では、人工膝関節置換術(TKA)が適応。
- 日本では年間12万件以上のTKAが実施されており、国家試験でも適応判断が問われる。
人工膝関節置換術(TKA)の適応やリハビリについて知りたい💡
別記事🫱『変形性膝関節症に対するTKAの適応と侵入方向・侵襲筋の関係』で解説🚶
(4)歩行分析と生体力学(KAM)
📝出題例
「膝内反モーメント(KAM)に関して正しいのはどれか。」
✅解説
KAM(Knee Adduction Moment)は、立脚初期に膝関節内側へかかるメカニカルストレスの指標です。以下のような条件でKAMが増加し、OA進行に寄与するとされています。
- 膝内反(O脚):荷重線が内側に偏り、関節内側に負担。
- 大腿外側筋群の筋力低下:膝外側支持性の低下。
- 体重過多:荷重そのものが増大し、KAM上昇。
国家試験では、KAMの理解だけでなく、歩行時にKAMを増加・軽減させる因子を選択肢から選ばせるような問題が出題されることがあります。
参考🫱日本整形外科学会. 変形性膝関節症診療ガイドライン 第3版. 2023年.
(5)鑑別・併存疾患
📝出題例
「膝OAの症状と類似する疾患はどれか。」
✅解説
変形性膝関節症は慢性進行性の疾患ですが、他の膝疾患と症状が類似しているため、鑑別が重要です。
- 関節リウマチ:朝のこわばり、多関節、左右対称性。
- 半月板損傷:クリック、ロッキング、膝折れ感。
- 骨壊死:中高年女性に好発。MRIで早期診断。
国家試験では、これらを画像所見や病歴の違いから見分けられるかが問われます。
参考🫱厚生労働省 難病情報センター・特発性骨壊死(大腿骨顆部)
✏️ 国家試験対策:演習問題+解説【全5問】
【第1問】画像所見
Q1. 変形性膝関節症において最も早期に出現するX線所見はどれか。
A. 骨棘形成
B. 骨硬化像
C. 関節裂隙狭小化
D. 軟骨下骨嚢胞
E. 骨髄浮腫
✅ 正解:A. 骨棘形成
📝 解説:
X線画像上で最も早期に現れるのは骨棘(osteophyte)形成です。軟骨の摩耗に伴って関節縁に新生骨が形成され、外側に突出します。関節裂隙の狭小化は進行例で見られる所見です。骨髄浮腫はMRI所見であり、X線では見えません。
参考🫱日本整形外科学会. 変形性膝関節症診療ガイドライン 第3版. 2023年.
【第2問】保存療法
Q2. 膝OAに対する保存的治療として、エビデンスに基づき有効性が最も認められているのはどれか。
A. 関節牽引療法
B. 温熱療法のみ
C. ステロイド内服療法
D. 大腿四頭筋の筋力強化訓練
E. 完全免荷と松葉杖歩行の指導
✅ 正解:D. 大腿四頭筋の筋力強化訓練
📝 解説:
大腿四頭筋の筋力低下は膝OAの疼痛や歩行障害に直結するため、運動療法(特に大腿四頭筋強化)は第一選択の保存療法とされています。FransenらによるCochraneレビュー(2015)でも、運動療法が疼痛軽減と機能改善に効果的とされています。
【第3問】病態と症状
Q3. 変形性膝関節症の代表的な症状として正しいのはどれか。
A. 夜間の強い安静時痛
B. 関節の炎症による全身倦怠感
C. 動作開始時痛(スターティングペイン)
D. 関節軟骨が痛覚を持つため疼痛が生じる
E. 関節水腫は見られない
✅ 正解:C. 動作開始時痛(スターティングペイン)
📝 解説:
膝OAの典型的な疼痛パターンは「動作開始時痛」です。座位や安静から立ち上がるときに痛みがあり、動作を継続すると一時的に緩和します。また、軟骨自体には痛覚がなく、痛みの主な発生源は滑膜・骨・靭帯などの周辺組織です。
参考🫱日本整形外科学会. 変形性膝関節症診療ガイドライン 第3版. 2023年.
【第4問】生体力学
Q4. 膝OAにおけるKAM(膝内反モーメント)に関して、誤っているものはどれか。
A. KAMが大きいほど内側関節の進行が早い傾向にある
B. 膝内反(O脚)ではKAMが増加する
C. 歩行中の体幹の側方移動はKAMを増加させる
D. 体重の増加はKAMを高める
E. KAMの抑制には歩幅の調整や外側楔状インソールが有効である
✅ 正解:C. 歩行中の体幹の側方移動はKAMを増加させる
📝 解説:
体幹を患側に側屈させると、外力の作用線が膝関節の内側から遠ざかり、KAMはむしろ低下します。つまり、側方移動はKAMの「回避戦略」としても用いられます。KAMを抑える方法として、外側楔状インソール、歩幅の短縮、スローペース歩行などがあります。
参考🫱日本整形外科学会. 変形性膝関節症診療ガイドライン 第3版. 2023年.
【第5問】鑑別疾患
Q5. 膝OAと症状が似ており、鑑別を要する疾患として最も適切なのはどれか。
A. 頸椎症性脊髄症
B. 関節リウマチ
C. パーキンソン病
D. 尿酸結晶沈着症(痛風)
E. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
✅ 正解:B. 関節リウマチ
📝 解説:
関節リウマチ(RA)は朝のこわばり、対称性、炎症性関節症状が特徴であり、膝OAと区別すべき疾患です。国家試験では、病歴・炎症反応・関節分布の違いを元に選択肢から正しい鑑別を選ばせるパターンが多く見られます。
参考🫱厚生労働省 難病情報センター「関節リウマチ」
国試対策で有名な一冊📚『理学療法士・作業療法士国家試験必修ポイント 専門基礎分野 臨床医学 2026 オンラインテスト付』(医歯薬出版)
💡 まとめ:変形性膝関節症の国家試験対策・総仕上げ
変形性膝関節症(膝OA)は、国家試験において毎年のように出題される最重要テーマの一つです。疾患の頻度の高さに加え、疫学、画像診断、治療法、生体力学、鑑別など複数の観点から問われるため、出題範囲が広く、基本的な知識の積み上げがカギとなります。
ここで、学習の要点を整理しておきましょう。
✅ 国家試験に頻出の重要ポイント
- 疫学:高齢女性・肥満・外傷歴などのリスク因子は確実に理解する
- X線画像所見:骨棘形成 → 関節裂隙狭小 → 骨硬化 → 骨嚢胞 の順に出現
- 保存療法:大腿四頭筋トレーニングは第一選択。NSAIDs外用薬やヒアルロン酸注射も有効
- KAM(膝内反モーメント):力学的負荷が進行に関与。歩行中の姿勢戦略やインソールで軽減可能
- 鑑別疾患:関節リウマチ、骨壊死、半月板損傷との違いを押さえる
📌 学習アドバイス
- まずは過去問を反復し、「どの観点が問われやすいか」に感覚をつかむことが重要です。
- 教科書的な理解だけではなく、画像、運動分析、治療選択の実践的判断力が試される問題にも慣れておくことが得点力につながります。
- 必ず最新のガイドライン(日本整形外科学会など)を参照して、現場基準に則った知識を身につけましょう。
この記事が国家試験対策の一助となり、読者の理解と得点アップにつながることを願っています。



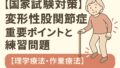
コメント