【 変形性股関節症 】は、関節疾患のなかでも特に国家試験(PT・OT)で頻出のテーマです。主に中高年の女性に多くみられ、加齢や発育異常、外傷などが原因となり、関節軟骨の変性と破壊が進行することで痛みや可動域制限が生じます。
国家試験では、臨床像、画像所見、治療法、運動療法、禁忌事項、術後管理などが幅広く問われるため、体系的な理解が不可欠です。
この記事では、変形性股関節症の基本情報と出題傾向を整理し、国家試験の出題パターンに沿った練習問題を交えて学習できる構成にしています。
📊 統計
【 変形性股関節症(hip osteoarthritis) 】は、高齢女性を中心に多くみられる運動器疾患であり、国家試験においてもその有病率や好発年齢、性差といった疫学的な知識が問われることがあります。
2006年に日本整形外科学会と日本リウマチ学会が実施した大規模研究「ROAD study(Research on Osteoarthritis Against Disability)」によると、日本人における変形性関節症の有病率は以下のように報告されています。
「X線上でKL分類グレード2以上の変形性股関節症を有する者の割合は、女性22.3%、男性9.1%であった」
🫱参考
また、同研究では、60歳以上の女性での発症率が特に高いことも指摘されており、国家試験でも「変形性股関節症はどの年代・性別に多いか」といった形式で設問化されることがあります。
さらに、2021年に発表された報告では、変形性股関節症の原因の多くが発育性股関節形成不全(DDH)に起因する二次性であることも確認されています。
🫱参考
変形性股関節症について詳しく知りたい場合は、別記事🫱『変形性股関節症とは?原因・手術・リハビリまでやさしく解説【医療職・学生向け】』を読むのがおすすめ🚶
✅国家試験対策Point
- 変形性股関節症は女性に多い(特に60歳以上)
- 日本では発育性股関節形成不全を背景とする二次性股関節症が多数
- X線上ではKL分類 Grade 2以上を基準とする
これらのデータは、国家試験で「臨床背景や患者プロファイルを選ばせる問題」や「疾患の原因分類」に関連して問われやすいため、数字や分類とセットで覚えておくと得点源になります。
⛰ 国家試験で問われる変形性股関節症の頻出テーマ一覧
変形性股関節症(hip osteoarthritis)は、理学療法士・作業療法士国家試験の整形外科分野において頻出の疾患です。特に次のような観点からの出題が多く、過去10年以上にわたって繰り返し問われています。
✅① トレンデレンブルグ徴候と中殿筋機能
最もよく出題されるのが、「トレンデレンブルグ徴候(Trendelenburg sign)」です。これは股関節外転筋、特に中殿筋の筋力低下を示す徴候で、歩行時に健側骨盤が下がる現象をいいます。
例題傾向:
- 「股関節疾患により、歩行時に骨盤が傾斜する。この原因となる筋はどれか」
- 「トレンデレンブルグ徴候が陽性の場合、弱化している筋は?」
本徴候は臨床実習やOSCE(客観的臨床能力試験)でも頻繁に観察される重要項目であるため、国家試験でも確実に出題されます。
トレンデレンブルグ歩行については別記事🫱『跛行とは?原因となる筋力低下・起こりやすい疾患・リハビリアプローチを徹底解説!』の中で解説🚶
✅② KL分類(Kellgren-Lawrence分類)とX線所見
国家試験ではX線画像の所見理解も重視されます。なかでも、「Kellgren-Lawrence(KL)分類」に関する設問が定番です。
KL分類とは、関節裂隙の狭小、骨棘形成、骨硬化、骨嚢胞などの程度に応じて0〜4に分類されるものです。
例題傾向:
- 「KL分類でGrade 3に相当する所見はどれか」
- 「関節裂隙狭小と骨棘形成がみられる場合のKL分類は?」
この分類は、画像読影力+病期理解の両方が問われる難所です。選択肢の中で「どの程度の変形か」を把握できるように、画像とセットで学習する必要があります。
✅③ 原因と分類(一次性・二次性)
「一次性と二次性の違い」は、基本的知識として押さえるべきポイントです。
- 一次性変形性股関節症:明確な原因がなく、加齢や長年の負担に起因。
- 二次性変形性股関節症:発育性股関節形成不全(DDH)や外傷など、原因が明確。
国家試験では、次のような出題形式が見られます。
例題傾向:
- 「発育性股関節形成不全を基礎疾患とするのはどれか」
- 「一次性と二次性の違いについて正しいものを選べ」
✅④ 手術療法:人工股関節置換術(THA)と禁忌姿勢
人工股関節置換術(THA)後のリハビリにおける禁忌肢位や動作についても、極めて高い頻度で出題されています。
具体的には、「屈曲90°以上・内転・内旋」の組み合わせが脱臼肢位となりやすいとされ、術後のADL訓練に影響します。
例題傾向:
- 「THA術後に避けるべき動作はどれか」
- 「脱臼予防のために指導すべき内容は?」
これらはリハビリ職種にとって臨床的にも重要であり、正確な知識が求められます。
THAとBHAの違いが知りたい方は、別記事🫱『変形性股関節症に対するBHA(人工骨頭置換術:Bipolar Hip Arthroplasty)とTHA(人工股関節置換術:Total Hip Arthroplasty)の違いとは?―侵入方向と侵襲筋に注目して解説―』を読むのがおすすめ🚶
✅⑤ 保存療法と運動療法の指導内容
国家試験では、「運動療法の適応・禁忌」に関する問題もよく出されます。
- 禁忌:重度の疼痛があるときの荷重運動
- 推奨:中殿筋・腸腰筋の強化、可動域維持
例題傾向:
- 「保存療法で行う運動療法の内容として不適切なものはどれか」
- 「関節保護のために指導すべき内容は?」
このように、「どれが誤りか?」を問うひっかけ問題が多いため、根拠を持った知識が求められます。
✅⑥ 疫学・性差・発症年齢などの背景知識
国試では基礎的なデータも出題されます。
例えば、以下のようなポイントが重要です。
- 変形性股関節症は女性に多く、中高年に好発
- 日本では発育性股関節形成不全が原因の二次性が多い
この分野は統計や疫学データの暗記がメインになるため、過去問から頻出データを押さえておきましょう。
🔎 出題キーワードとその解説【国家試験頻出】
国家試験で変形性股関節症が出題される際は、キーワードごとに深掘りされた理解が求められます。ここでは特に頻出のキーワード5つを解説します。
🟦トレンデレンブルグ徴候(Trendelenburg sign)
✔ 国家試験での問われ方:
- 「跛行を認める患者において、立脚側の中殿筋が弱い場合、どの徴候が陽性となるか?」
- 「トレンデレンブルグ徴候陽性時に関与する筋はどれか?」
✔ 解説:
中殿筋の筋力低下により、患側に荷重した際に健側の骨盤が下がる現象。片脚立位での骨盤の水平保持ができないことから歩行時に“左右に揺れるような跛行”が出現します。
トレンデレンブルグ徴候は、筋力低下性跛行の代表例として、画像や記述形式で問われることがあります。
🟦Kellgren-Lawrence(KL)分類
✔ 国家試験での問われ方:
- 「Grade 3に該当するX線所見として正しいものはどれか」
- 「関節裂隙狭小・骨硬化・骨棘形成がある状態は何グレードか?」
✔ 解説:
KL分類は、X線所見に基づいた変形性関節症の進行度分類。以下がその要点です:
| グレード | 特徴 |
|---|---|
| 0 | 正常 |
| 1 | 疑わしい骨棘形成 |
| 2 | 明瞭な骨棘形成、関節裂隙は正常またはやや狭小 |
| 3 | 複数の骨棘、関節裂隙の明らかな狭小、骨硬化 |
| 4 | 著しい関節裂隙狭小、骨変形 |
国家試験では、X線写真+所見の読み取り問題も出題されるため、各グレードの特徴を覚えておく必要があります。
🟦一次性・二次性の違い
✔ 国家試験での問われ方:
- 「発育性股関節形成不全に続発する股関節症はどれか?」
- 「一次性変形性関節症に分類されるものは?」
✔ 解説:
- 一次性:明らかな原因がなく加齢や長期負荷によって発症
- 二次性:発育性股関節形成不全(DDH)、外傷、炎症性疾患など原因が明らか
日本では、変形性股関節症の約80%以上が二次性(特にDDH)であると報告されています
(参考:日本整形外科学会, 変形性股関節症診療ガイドライン, 2016年)
🟦人工股関節全置換術(THA)と禁忌肢位
✔ 国家試験での問われ方:
- 「術後脱臼を防ぐために避けるべき動作はどれか?」
- 「THA術後に安全な動作指導として正しいのはどれか?」
✔ 解説:
THA後の脱臼肢位(特に後方アプローチ)には、股関節屈曲90°以上、内転、内旋の組み合わせが含まれます。
ベッドからの起き上がり動作や、和式トイレの使用、あぐら姿勢などがリスクとなります。
試験では、「どの動作が危険か」または「正しい指導はどれか」と問われることが多く、術式ごとの注意点の理解が問われます。
🟦保存療法における運動療法と禁忌
✔ 国家試験での問われ方:
- 「変形性股関節症の保存療法として適切なものは?」
- 「筋力強化の対象となる筋はどれか?」
✔ 解説:
保存療法では、痛みのない範囲での筋力トレーニング(特に中殿筋・腸腰筋)が基本。
また、過度な負荷・無理なストレッチは症状悪化のリスクがあるため禁忌とされます。
国家試験では、「適切な運動」と「禁忌運動」が選択肢に混在することが多く、誤答を誘導するパターンとして注意が必要です。
運動器・整形疾患を分かりやすく、イラスト付きで学べる✏️手元に置いておきたい一冊📚
『病気がみえる vol.11 運動器・整形外科 第2版』(医療情報科学研究所、MEDIC MEDIA)
🏥 手術療法(THA)と国家試験での問われ方
変形性股関節症が進行し、保存療法で効果が得られない場合の最終的治療法が「人工股関節全置換術(Total Hip Arthroplasty:THA)」です。国家試験では、この手術療法に関連する設問が繰り返し出題されており、特に「禁忌肢位」や「脱臼予防の指導内容」など、実際の臨床でPT・OTが担当する範囲が問われます。
🟦THA(人工股関節置換術)とは
THAは、損傷・変形した股関節の骨頭および臼蓋を人工関節に置換する外科的手術です。
高齢者に多い変形性股関節症において、痛みの除去と可動域の改善、日常生活の質の向上を目的とします。
THAとBHAの違いが知りたい方は、別記事🫱『変形性股関節症に対するBHA(人工骨頭置換術:Bipolar Hip Arthroplasty)とTHA(人工股関節置換術:Total Hip Arthroplasty)の違いとは?―侵入方向と侵襲筋に注目して解説―』を読むのがおすすめ🚶
📌参考:日本整形外科学会『変形性股関節症診療ガイドライン2020』
🟦国家試験で問われる視点①:脱臼を防ぐための肢位制限
THA術後、最も注意すべきなのは人工関節の脱臼です。国家試験では、以下のような脱臼肢位の知識が問われます。
✔ 脱臼しやすい肢位(後方アプローチの場合):
- 股関節屈曲 90°以上
- 股関節内転(患側への横倒し)
- 股関節内旋(つま先が内向き)
これらが組み合わさった動作、たとえば「あぐら」「しゃがみ動作」「和式トイレ」などは術後直後に避けるべきとされます。
❗国家試験での出題例(過去問傾向):
- 「THA術後の脱臼を予防するために、避けるべき姿勢はどれか?」
- 「ベッド上で安全な体位として適切でないのはどれか?」
このように、「禁忌肢位の組み合わせ」を理解しているかが問われます。
🟦国家試験で問われる視点②:術後リハビリの進め方
PT・OTがTHA術後に関わる範囲として、以下のようなリハビリ介入が出題されます。
✔ 術後の基本的リハビリ内容:
- 早期離床(術後翌日〜):全身状態の安定と二次的廃用症候群を防ぐ
- 立ち上がり・歩行練習:禁忌肢位を避けながら荷重訓練
- 階段昇降指導:「昇るときは健側、降りるときは患側」の原則
国家試験では、術後のリハ指導として正しいもの/間違っているものを選ばせる形式がよく見られます。
❗例題パターン(ひっかけ問題の代表):
- 「THA術後1日目、患者に指導すべき動作として不適切なのはどれか」
- 「歩行練習時に留意すべき動作はどれか」
このような問題では、選択肢の中に「正解に見えるが脱臼を誘発する肢位」が混ざるため、臨床知識が問われます。
🟦国家試験で問われる視点③:指導内容の記憶と実用性
近年の国家試験では、「正しい教育指導内容」に関する設問も増えています。
✔ 重要指導内容:
- 座るときは膝より股関節を低くしない(高座椅子を使用)
- 靴下を履く際は前屈を避け、靴べら等を使用
- 起き上がり動作は健側を下にした側臥位で
❗実際の過去出題例(形式)
- 「THA術後の家庭復帰指導で不適切な内容はどれか?」
- 「ADL指導の内容として最も適切なものは?」
このような問題では、「患者が日常で行う動作の中で、脱臼リスクがあるかどうか」を臨床視点で判断する能力が試されます。
✅ THAと国家試験の対策ポイント
| 項目 | 出題される主な観点 |
|---|---|
| 禁忌肢位 | 屈曲90°以上・内転・内旋の組み合わせ |
| 術後指導 | 離床タイミング、歩行介助、ADLの安全性 |
| 教育指導 | ベッドからの起き方、座位姿勢、靴の履き方 |
これらの知識は、国家試験だけでなく臨床現場でも即戦力となる内容です。
暗記だけでなく、「なぜそれが禁忌か?」という根拠を意識しながら学習を進めましょう。
💡 臨床推論型問題への対策:症状・画像・評価の読み取り
近年の理学療法士・作業療法士国家試験では、単なる暗記では解けない「臨床推論型問題」の出題が増加しています。
変形性股関節症(OA of the hip)も例外ではなく、症例ベースの設問が多く見られます。
ここでは、臨床推論問題で問われやすい視点と、その対策法について解説します。
🟦【1】症状から疾患像をイメージする力をつける
国家試験では、患者の年齢・性別・訴えなどから疾患を推定させる問題がよく出題されます。
❗例題形式(よくあるパターン):
「60歳女性。数年前から右股関節の違和感を感じていたが、最近は歩行時に右股関節の痛みが出現。診察ではトレンデレンブルグ徴候が陽性であった。」
このような記述のあとに、「最も考えられる疾患名は何か?」や「どの筋の機能が低下しているか?」などを問う形式です。
✔ 対策ポイント:
- 高齢女性、荷重時痛、トレンデレンブルグ徴候 → 変形性股関節症を疑う
- 「立ち上がり」「方向転換」「長時間歩行」時の痛み → 股関節の変性進行
- 単なる症状の暗記ではなく、「誰に、どのような症状が、どのタイミングで出現しているか」を読む練習が必要
🟦【2】画像(X線)所見の読解力を身につける
変形性股関節症に関しては、X線画像の所見を読み解く問題も出題されます。とくにKellgren-Lawrence(KL)分類の段階ごとの変化を知っておくことが重要です。
❗出題傾向
- 「画像所見として誤っているものはどれか?」
- 「この所見に該当するKL分類はどれか?」
✔ よく出る画像所見:
- 関節裂隙の狭小化
- 骨棘(osteophyte)形成
- 骨硬化像(sclerosis)
- 骨嚢胞(subchondral cyst)
✔ 対策ポイント:
- 実際のX線画像を参考に「どの所見がどのグレードに対応するか」を視覚的に理解
- KL分類とJOA分類を混同しないように整理して覚える
🟦【3】身体所見・検査法からの評価問題への備え
身体評価に関する設問では、股関節可動域の制限や跛行の特徴を正しく理解しているかが問われます。
❗問われやすい観点
- 股関節の内旋・屈曲制限 → OAの初期症状
- トレンデレンブルグ徴候 → 中殿筋筋力低下
- 骨盤の傾斜・体幹の代償 → 筋力低下性跛行の評価
✔ 代表的検査と国試での出題例:
| 検査名 | 出題される内容例 |
|---|---|
| トレンデレンブルグテスト | 陽性の判断基準、関連筋 |
| Patrick(FABER)テスト | 股関節疾患と仙腸関節障害の鑑別 |
| Elyテスト・Thomasテスト | 股関節伸展制限の評価、代償動作の読み取り |
🟦【4】選択肢の文章読解力を高める
臨床推論型問題の選択肢は、一見正しそうな内容のなかに“落とし穴”があるケースが多いです。
❗例
- 「THA術後、和式トイレの使用を指導した」→ ❌ 脱臼リスクあり
- 「股関節の可動域拡大のため、積極的にストレッチを行う」→ ❌ 炎症期や疼痛が強い時期には不適切
✔ 対策
- 消去法で選ぶだけでなく、「その記述が安全か? 臨床的に妥当か?」を想像して解答
- 選択肢の語尾の違い(〜しない、〜するべき)を丁寧に読み取る
✅ 臨床推論問題の得点力を上げるには?
| 学習項目 | 具体的対策 |
|---|---|
| 症状読解 | 年齢・性別・訴えから疾患像を推定する力をつける |
| 画像診断 | KL分類の段階を視覚で記憶・読影問題に慣れる |
| 身体評価 | トレンデレンブルグや可動域制限の臨床的意味を理解 |
| 読解力 | 設問文と選択肢の表現に慣れ、ひっかけに注意する |
変形性股関節症における臨床推論型問題は、単なる暗記では対応できない領域です。
症例の流れを読み解きながら、「なぜこの所見が出るのか」「どの筋・関節が関係するのか」を自分の言葉で説明できる力をつけておきましょう。
✏️ 過去問類似の練習問題(解説付き)
以下の練習問題は、国家試験の出題傾向を分析して作成された4択形式です。各問題には正答と詳細な解説をつけていますので、なぜ正解なのか・なぜ他の選択肢が誤りなのかを確認しながら取り組んでみてください。
【問題1】
60歳女性。右股関節の痛みを主訴に来院。関節裂隙の狭小、骨棘形成、骨硬化がX線画像で確認された。この所見に最も該当するKL分類はどれか。
A. Grade 1
B. Grade 2
C. Grade 3
D. Grade 4
正解:C. Grade 3
解説:
KL分類においてGrade 3は、「中等度の変形」を示し、関節裂隙の明らかな狭小化、複数の骨棘、骨硬化像の出現が特徴です。Grade 2は軽度の骨棘形成で、関節裂隙は保たれています。Grade 4では関節裂隙の消失と骨変形が著明となります。
【問題2】
変形性股関節症患者が歩行中に健側骨盤の下制を認めた。このとき、機能低下している筋として最も適切なのはどれか。
A. 大腿四頭筋
B. 大臀筋
C. 中殿筋
D. 腸腰筋
正解:C. 中殿筋
解説:
中殿筋は股関節外転筋として、片脚立位時に骨盤を水平に保つ役割を担います。この筋が機能低下すると、立脚期に健側の骨盤が落ちる「トレンデレンブルグ徴候」が陽性になります。これは国家試験で非常に頻出の設問です。
【問題3】
変形性股関節症の人工関節置換術(THA)後、脱臼予防のために最も注意すべき肢位の組み合わせはどれか。
A. 屈曲・内転・外旋
B. 屈曲・内転・内旋
C. 伸展・外転・外旋
D. 伸展・内転・外旋
正解:B. 屈曲・内転・内旋
解説:
THA(特に後方アプローチ)では、股関節屈曲90°以上・内転・内旋の組み合わせが脱臼のリスクを高めます。和式トイレやあぐらの姿勢、深く腰をかがめる動作などが該当します。選択肢Aの「外旋」は誤りです。
【問題4】
THA術後1日目に患者へ指導すべき内容として、不適切なものはどれか。
A. ベッドから起き上がる際は健側を下にする
B. トイレは洋式を使用するようにする
C. 歩行器で患側から先に出して歩くように指導する
D. 靴を履く際は前屈して自分で履くように勧める
正解:D. 靴を履く際は前屈して自分で履くように勧める
解説:
前屈動作(屈曲+内転+内旋)は脱臼肢位であり、THA術後早期には禁忌です。靴の着脱には靴べらや道具を使う、介助を受けるなどの工夫が必要です。その他の選択肢は、基本的に正しい術後指導の内容です。
【問題5】
変形性股関節症における保存療法として最も適切な運動療法はどれか。
A. 大殿筋のストレッチを中心に行う
B. 中殿筋と腸腰筋の筋力強化を行う
C. 股関節を最大可動域で反復運動する
D. 患側下肢にジャンプ動作を指導する
正解:B. 中殿筋と腸腰筋の筋力強化を行う
解説:
保存療法では、股関節の安定性を保つ中殿筋や腸腰筋の筋力強化が有効です。AやCは疼痛がある場合や可動域制限がある患者には不適切であり、Dは関節への過度な負荷となります。
✅ ポイントまとめ
- 問題文の症例描写・語尾表現(正しい/誤っている)に注意
- 正解だけでなく誤答選択肢がなぜ間違っているかを理解する
- 出題パターンに慣れながら、臨床知識との結びつきを意識する
国試対策に定番のこの一冊📚『クエスチョン・バンク 理学療法士・作業療法士国家試験問題解説 2026』(医療情報科学研究所、MEDIC MEDIA)
✏️ よくある誤答パターンとその対策法【国家試験対策】
変形性股関節症に関する国家試験では、基礎知識を問う設問だけでなく、「一見正しく見える選択肢」による誤答誘導パターンが数多く存在します。
この章では、特に多い誤答パターン5つを取り上げ、それぞれの間違いやすい理由・正しい考え方・覚え方を紹介します。
🟥【パターン1】トレンデレンブルグ徴候と大殿筋の混同
❌誤答例:
「股関節疾患により骨盤が傾斜する。機能低下しているのは大殿筋である」
✅正しい知識:
骨盤の傾斜は中殿筋(中殿筋+小殿筋)の機能低下によって起こる
→ これは股関節外転筋として、片脚立位で骨盤を支える役割を持つ。
📝対策:
「トレンデレンブルグ徴候 = 中殿筋」と反射的に結びつけるように訓練。
大殿筋は主に股関節伸展を担当するため、歩行の立脚初期などとは役割が異なることを明確に整理しましょう。
🟥【パターン2】KL分類と画像所見の取り違え
❌誤答例:
「関節裂隙の狭小と骨硬化がみられる → KL分類 Grade 2」
✅正しい知識:
- Grade 2:明瞭な骨棘形成、関節裂隙は正常〜やや狭小
- Grade 3:明らかな関節裂隙の狭小化+骨棘+骨硬化(このケース!)
📝対策:
KL分類は「段階が上がるごとに所見が加わる」と整理するのがコツ。
図解やX線写真で繰り返し学習し、視覚で覚えると記憶の定着が早まります。
🟥【パターン3】THA術後の動作指導で“和式トイレOK”と誤認
❌誤答例:
「THA術後、和式トイレは脱臼肢位を避ければ使用できる」
✅正しい知識:
和式トイレは、屈曲+内転+内旋の複合動作が必要になるため、THA術後の脱臼リスクが非常に高い。
→ 必ず「洋式トイレの使用」を指導
📝対策:
「脱臼肢位」=「しゃがむ・あぐら・前屈する」は原則NGと覚える。
日常動作の中で患者がやりがちな動作を禁止できる視点を持ちましょう。
🟥【パターン4】保存療法での“無理な可動域拡大”の選択
❌誤答例:
「変形性股関節症においては、可動域制限を防ぐために積極的にROM訓練を行う」
✅正しい知識:
痛みや炎症がある時期に強いストレッチを行うと、症状悪化や関節破壊の進行を招くリスクがある。
→ 保存療法では「疼痛のない範囲」で筋力強化と可動域維持を行うのが原則。
📝対策:
選択肢に「積極的に・強く・最大限に」などの表現があるときは注意!
→ リスクとバランスの観点から考えること
🟥【パターン5】内旋制限と股関節疾患の結びつけの弱さ
❌誤答例:
「股関節疾患では外旋の制限が出る」
✅正しい知識:
変形性股関節症の初期には、内旋・屈曲制限が起こるのが典型。
→ 診断的にも、股関節内旋の制限が早期発見の鍵とされている。
📝対策:
「変形性股関節症の初期 = 内旋・屈曲制限」を定型句として覚える。
Patrickテストでの痛みや、内旋ROMの減少をセットで押さえると◎。
💡 誤答パターンを“先に知っておく”のが合格への近道!
| 誤答パターン | 正しい対応 |
|---|---|
| 筋肉の混同(中殿筋・大殿筋) | 作用・役割を整理し、機能で覚える |
| KL分類の混乱 | グレードごとの所見を段階的に暗記 |
| 術後指導の誤認 | 禁忌動作を明確にしておく |
| 保存療法の過剰解釈 | 「疼痛のない範囲」での運動と記憶する |
| 初期症状の誤認 | 内旋・屈曲制限を確実にリンクさせる |
国家試験では、「正しい知識」だけでなく「間違えやすいパターン」を知っておくことが、合格へのショートカットになります。
過去問を解きながら、自分がこのような誤答をしていないかを常に振り返って学習していきましょう。
🌎 国家試験対策としての学習戦略まとめ【変形性股関節症】
変形性股関節症は、国家試験でも頻出テーマの一つです。単なる知識の暗記ではなく、臨床像の理解・画像読影・術後管理・運動療法指導など、多岐にわたる内容が問われます。
ここでは、合格のために効率的かつ実践的な学習ができるよう、出題傾向の整理と学習法のポイントをまとめます。
🟦出題の全体傾向
| 分野 | 出題例 | 難易度 |
|---|---|---|
| 解剖・運動学 | 中殿筋の機能、可動域制限、跛行分析 | ★★☆☆☆ |
| 疾患特性 | 原因(一次性/二次性)、症状進行 | ★★★☆☆ |
| 画像所見 | KL分類とX線所見のマッチング | ★★★★☆ |
| 手術療法 | THAの脱臼肢位、ADL指導 | ★★★★☆ |
| 臨床推論 | 症例文からの疾患特定、評価選択 | ★★★★★ |
🟦国家試験対策の学習ステップ
【ステップ1】基本知識の定着(語句・定義)
- 変形性股関節症の定義、症状、リスク因子を教科書ベースでしっかり理解
- KL分類やJOAスコアなどの分類・評価法は表にして反復暗記
【ステップ2】画像・動画での視覚学習
- X線画像を見ながら、各グレードの違いを視覚的に覚える
- トレンデレンブルグ徴候などは動画や実技映像で動きを理解する
【ステップ3】問題演習で出題形式に慣れる
- 過去問や模擬問題を使って、「なぜ間違えたか」まで分析
- 特に、正解を選ぶ力だけでなく、誤答を排除する読解力を鍛える
【ステップ4】暗記から「臨床想像」への変換
- 「60代女性が内旋制限を訴えたら?」→変形性股関節症を即イメージ
- 「和式トイレを使いたいと言ったら?」→THA術後なら危険と判断できるか
🟦スキマ時間学習にもおすすめな内容
- 語呂合わせで覚える脱臼肢位:「くないない(屈曲・内転・内旋)で危険!」
- 中殿筋の作用と歩行フェーズ:「中殿筋=片脚立位時の骨盤安定」
- KL分類の段階表はスクショ&スマホ待受にして反復視覚化!
✅ 変形性股関節症で差がつくのは「臨床視点」
変形性股関節症は、覚えるべき知識量は限られています。
しかし、知識を臨床判断に応用できるかどうかで得点に大きな差がつきます。
- 問われているのは、ただの知識ではなく「理解と応用力」
- 症例問題は、「患者を目の前にして自分ならどうするか」で考える
- 誤答パターンに先回りして対応できるかが合否を分ける
国家試験対策としてはもちろん、臨床現場でも使える知識としてしっかりと身につけていきましょう。

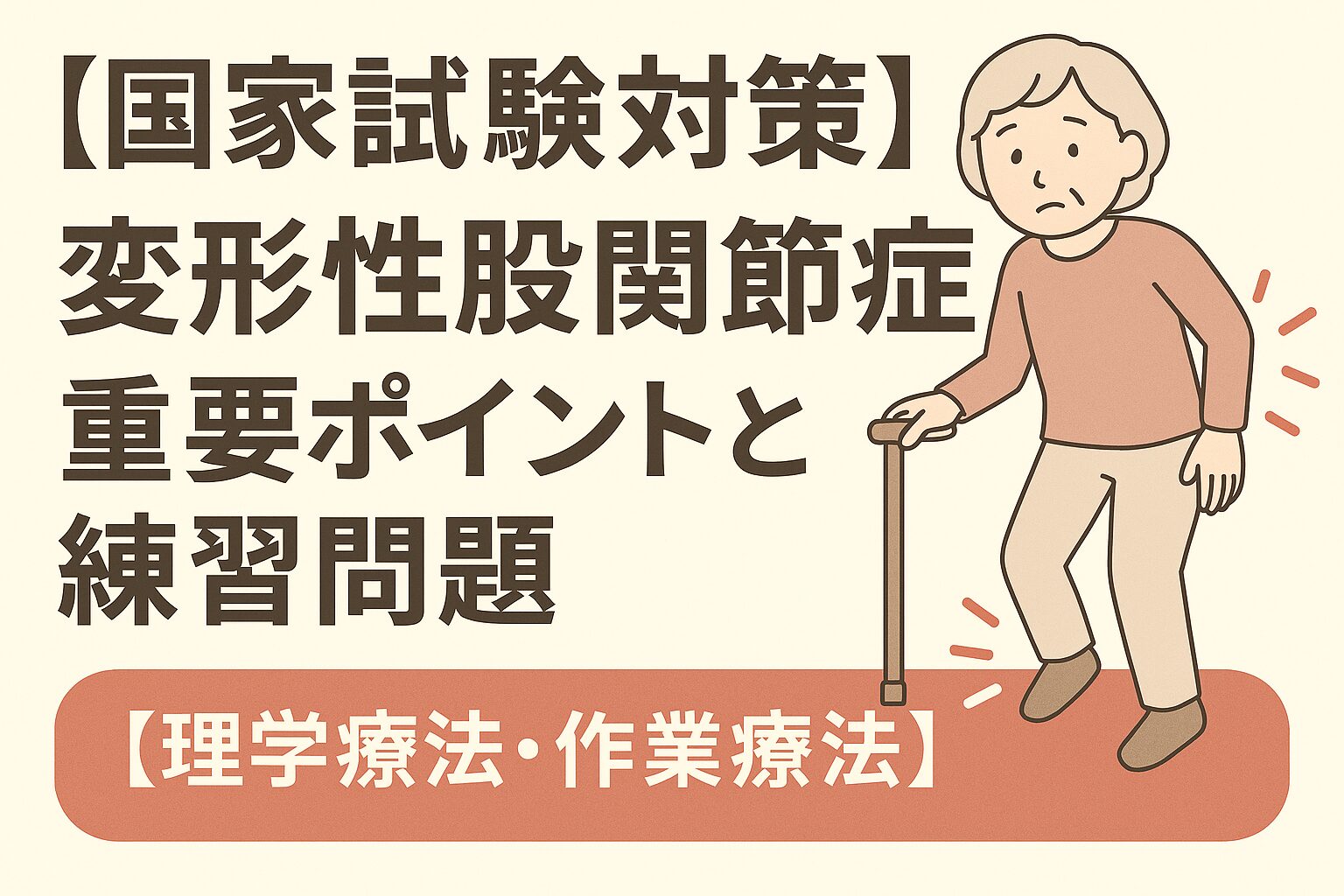
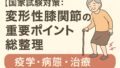

コメント